
© The Kyoto Costume Institute, photo by Toru Kogure
画像にマウスカーソルを乗せると拡大します。
ドレス(ローブ・ア・ラ・フランセーズ)
1760年頃(素材1735年頃)- イギリス
- 素材・形状特徴
- クリーム色に植物文様の絹ブロケード。二段のパゴダ型袖。共布のペティコート。
- 収蔵品番号
- AC830 78-24-5AB
絹ブロケードのローブ・ア・ラ・フランセーズ。多色の植物モチーフの文様部分には「ポワン・ラントレ(point rentrés)」と呼ばれる織布の技法が使われている。ポワン・ラントレは、絵画の原理が織布に応用されたもので、濃い色糸と淡い色糸を互い違いに入り組ませることで陰影を表現し立体感を出す技法である。この技法が用いられた最初期の事例として見出されているのは、リヨンの絹織物デザイナー、ジャン・ルヴェル(Jean Revel)による1733年の紋意匠図(方眼紙上に紋様が表されたもの)である(Jolly 2002:12)。この技法はイングランドにもすぐさま伝播し流行した。
このドレスの織物は、ロンドンのイーストエンドに位置するスピタルフィールズで織られたと推定されている。スピタルフィールズは当時ユグノー(フランス人プロテスタント)が多く移り住んでいた地である。1685年、宗教的な寛容策であった「ナントの勅令」(1598年発令)がルイ14世により廃止され、迫害を恐れたユグノーが国外に脱出し、移住先の一つとなったのがスピタルフィールズだった。ユグノーの中には高い技術を持った熟練職人も多く含まれており、スピタルフィールズでは高度な織布技術を要する絹織物業が営まれるようになった。本品のような白地の絹織物はスピタルフィールズ製に多く見られる。
なお、本品の文様が左右逆に反転して織り出された織物が使われたドレスが、イギリスサリー州のチャーツィー・ミュージアムに収蔵されている。
参考文献
Anna Jolly, Seidengewebe des 18. Jahrhunderts II Naturalismus, Abegg-Stiftung, 2002
Peter Thornton, "Jean Revel: dessinateur de la grande fabrique", Gazette des Beaux-Arts, July 1960, pp. 71-86.
佐野敬彦編『イギリスの染織――ヴィクトリア&アルバート美術館 第1巻 中世-ロココ(1200-1750)』学習研究社、1980年
須永隆『プロテスタント亡命難民の経済史――近世イングランドと外国人移民』昭和堂、2010年
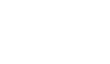 Digital Archives
Digital Archives




















